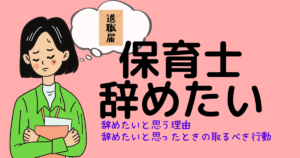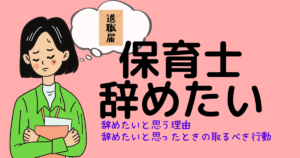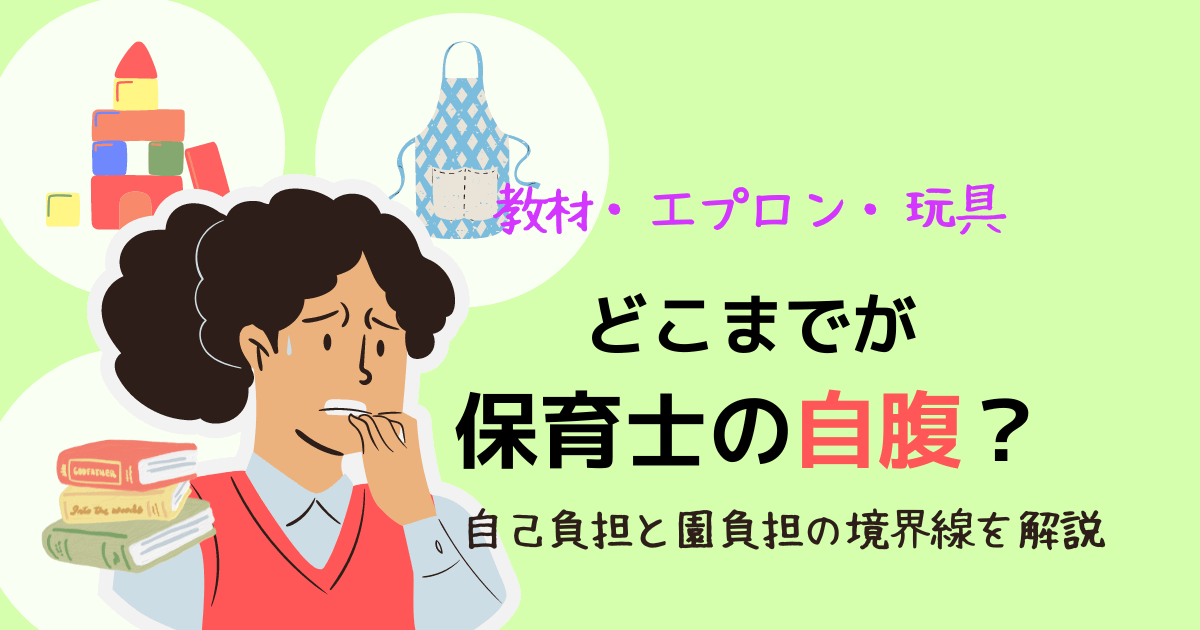保育士になって、絵本やエプロンを自腹で買ってる。こういうのって保育園が負担してくれるんじゃないの?
絵本やエプロンは仕事に必要ですが、自腹で購入している保育士は多いです。高いとはいえない保育士の給料で、自己負担になるのはきついですよね。
驚くかもしれませんが、仕事に必要なものであっても誰が負担するかは法律で定められていません。つまり保育園側が自由に決める権利があるということ。とはいえ、もちろん会社側は何でもかんでも保育士に自己負担させていいというわけではありません。
この記事は、自己負担で自分が損をしていないかどうかがわかるような内容になっていますのでぜひ最後までご覧ください。自腹を減らす方法もあわせて紹介しますので参考にしてもらえると嬉しいです!



この記事を書く私は、保育歴8年の元保育士。私も過去に、材料や教材を自腹で購入し、悩んだ過去があります。
でも、途中から「それはおかしい」と思うようになり、上司に経費の申告をするようになりました。申告する勇気をもつことも脱・自腹には大切です。
- 自己負担と園負担の境界線
- 保育士がよく自腹で購入するアイテム
- 保育士の自腹を減らす方法3選
不必要な出費を減らして、自分のお金を大切にしていきましょう。
【保育士の疑問】自腹と園負担の境界線は?


冒頭でも少し触れましたが、自腹と園負担の境界線は保育園側がにぎっています。



仕事に必要なものは経費でおりるって、法律か何かで決まってるんじゃないの!?
と思う方も多いでしょうが、労働基準法で経費と自己負担のボーダーラインは、明確に規定していません。
したがって、自己負担でよく問題にあがる絵本代や教材費、エプロン代などは、保育園の判断で労働者に負担させても法律上は問題なしということ。
しかし自己負担に関することを、労働基準法第89条(五)で以下のように定めています。
第九章 就業規則 (作成及び届出の義務)
第八十九条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
五 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
e-Gov 法令検索
会社側が仕事で使う道具などを労働者に負担させる場合、その詳細をしっかりと就業規則に記載し、労働者に提示しなくてはいけません。
つまり、絵本やエプロンなどを保育士に負担させる場合は、以下のような内容を就業規則に記載する必要があります。
- 「子どもたちに読む絵本はあなた負担になります」
- 「エプロン着用の義務がありますが、エプロン代はあなたが負担してください」
- 「活動で使う材料費は園では負担しないので、自腹で購入してください」
提示した条件に保育士が納得した上で、初めて「自己負担」が成立するのです。
逆にいうと、就業規則に負担に関する記載をしなければ、園は保育士に仕事に必要なものを買わせてはいけないということ。これに反すれば、法律違反になります。
しかし規則を明確にしないまま、「保育士が自主的に買ったもの」として扱い、自腹を黙認している保育園は多いでしょう。これを良しとしてしまうと、ただただ保育士が損をしているということになります。
閲覧方法は、事業所内への掲示、書面での交付、パソコンでの閲覧など様々。法律により就業規則は、労働者が自由に閲覧できるようになっているので、好きなときにチェックができるはずです。
もし会社側が閲覧を拒否した場合、法律違反になります。
そもそも、会社で必要なものは会社で負担するのが一般的。労働者への負担が大きいと、労働者のやる気が低下し、会社への不信感にもつながるからです。



何でもかんでも保育士に買わせる保育園やお金のことを曖昧にする園は要注意。信頼性に欠けますよね。
【自腹に限界】保育士が園負担を強く願う保育のアイテム5つ


ここでは保育士がよく自腹で購入するアイテムを5つを発表。SNS上であがっていたリアルな声も合わせてお伝えしますね。
- 絵本
- エプロン
- 教材
- 材料
- おもちゃ
絵本
絵本を自腹購入している保育士は多いと聞きます。絵本の数が不十分かつ絵本を購入する気配が園にない場合に保育士が自腹で購入するケースが多いでしょう。
絵本は子どもの成長に欠かせないもの。保育の中で大切な教材のひとつとして扱われています。したがって、保育園が負担して絵本を買ってほしいところ。
新品の絵本であれば1冊1000円以上するものも。1000円の絵本を毎月1冊、自腹で購入することになれば、年間で1万2000円の出費になります。絵本は行事のもの、季節のもの、子どもたちの発達にあっているもの、子どもたちが興味のあるものなど、選び方の視点がさまざまあるので実際にはもっと購入する機会が多いでしょう。
大変な出費にも関わらず、「子どもたちのために目的にあった絵本を読んであげたい」という想いから、自腹で絵本を購入する保育士は少なくありません。
以下のつぶやきは保育士のリアルな声です。
前の会議で上司がヤル気のある保育士のクラスは絵本が揃ってると言ってた。絵本の冊数が保育士のヤル気?本来なら保育で必要なものは園で買って欲しい。必要経費なはず。保育園っておかしいことだらけ。普通の会社なら備品で用意されるべきもののはず。保育士の自腹なんてあり得ない!
— ゆう (@taekomiyu) May 9, 2020



絵本が充実している保育園もたくさんあります。はじめから絵本が揃っている園だと、保育士の負担も少ないですよね。
エプロン
エプロンの指定がない保育園で、エプロンを自腹で購入する保育士は多いそうです。
入社するときに、エプロンについて特に説明がなければ、「エプロンは自分で買うものなんだ」と解釈してしまう人が多いでしょう。
保育士はエプロンの着用が義務付けられていることが多いので、「仕事の制服」としてエプロン代を支給してほしいですよね。(全額が無理ならせめて、一部支給だけでも…。)
エプロンは衣料店などの店頭では、1000円〜2000円。保育士のエプロン専門誌にのっているエプロンは4000円近くします。2000円のエプロンを年に5着買い換えると年間で1万円の出費です。
エプロンを身だしなみのひとつとして、定期的に買い替えを行なっている人も多いでしょう。エプロンは単価が高いため、保育士の出費がかさむアイテムのひとつです。
以下のつぶやきは保育士のリアルな声。
本当に【ここが変だよ日本の保育園】です。
— あや (@aya_hoikushi) August 12, 2021
大人になっても大切な根っこの部分を育てる大切な子どもたちを保育してるのに低賃金。
しかも、自腹も多い。苦笑
百均なのにいつもゼロ1個多くお買い物。
エプロンもよれよれの着たくないし、エプロン代もままならないよ🥲#保育士 https://t.co/9j0dhhxtSA
#手取り15万円
— 元保育士の女🍺🐈 (@hoikushidorei) September 24, 2019
元 #保育士、笑えない…
勤務中の服やエプロン代を捻出するのに四苦八苦
ブラ等のインナー.下着類は激安の物しか買えない
UNIQLOですら高い…
ジュース1本買う事すらためらう
あ、副業(バイト)してました
やむなし
保育士の給料じゃ一人暮らしムリでした#貧困保育士



エプロンを貸し出している保育園もありますよね。そのシステムだと、エプロン代がかからなくていいかも!
材料
製作活動で使う画用紙や折り紙、モールなどを自分で用意する保育士は多いでしょう。
事前に申告すれば購入の許可がおりる園もたくさんあると思いますが、上司がお金に厳しい人や怖い人である場合は声がかけにくいですよね。
製作活動は定期的に行われ、そこで使う材料は数百円で買えることが多いと思います。そのような申告回数の多さや申告する額の低さが、「言いづらさ」をより強めているかもしれません。
とはいえ、教材費の実費を重ねていくと、かなりの出費になっていくので注意が必要です。



言いにくい環境を改善することも上司の仕事。なんでも相談しやすい保育園が理想ですね。
教材
運動会・発表会で使うCDを、保育士が自腹で用意する、という話はよく聞きます。活動で使うダンス曲のCDやピアノの楽譜なども実費で用意する人もいるでしょう。
音源は行事の進行や活動に欠かせないもの。自腹で用意している人が「保育園が負担するものでは?」と疑問に感じるのは当然でしょう。
CDは2000円以上するものが多いです。単価が高いので、1回の出費でも負担が大きいですよね。
以下のつぶやきは保育士のリアルな声です。
TSUTAYAで借りてきたCDをやいてる…はあ、保育士自腹で用意するもの多すぎ無理なんだが
— あ、無理な保育士 (@sgtyametee4) March 1, 2022
それで、会社も精一杯やってる?保育園らしくなった?
— ま (@tumtum_nya) October 24, 2018
全部保育士の自腹だよ。クラスに置いてるCDデッキもおもちゃ入れてるカゴも全部保育士が持ってきたんだよ。
壁面や製作に使ってる画用紙も全部自分の。室内遊びできる物も水遊びできる物もないから、全部材料自費で買ってきて手作り。ふざけるな。
おもちゃ
保育園に不可欠なオモチャを保育士が購入することもあるそうです。これは、明らかにおかしいですよね。保育士がオモチャを買う理由は、保育園にオモチャが全然そろっていないからでしょう。
置かれているオモチャが壊れたもの、いつから使用しているか分からないほど古いものばかりの園も存在します。また発達や子どもの姿などを無視して、年中同じオモチャを使っている園も。
オモチャの購入を渋る保育園は少なくありません。新しいオモチャは1万円以上するものも多く単価が高いからです。ひとつ買うと他のクラスからも要望がくる可能性を心配して、オモチャを買うそぶりを見せない上司もいるはず。
そんな状況から「これでは、子どもがかわいそうだ」と思い、保育士が実費でオモチャを購入する流れになるのでしょう。
以下のつぶやきは保育士のリアルな声です。
延長保育
— おにぎり姫 (@7ipZiO13JnthmSf) February 24, 2022
どう過ごしてますか?
延長利用してるお子さんはほとんど早朝からいるわけでしかも毎日なのでおもちゃも飽きてる様子
延長時のみの特別なおもちゃももう見向きもせず保育士自腹の持参のおもちゃを使ってます
パネルや絵本等もしますが正直ネタ切れ
乳児で何かあったら教えて下さい🙏
保育士の自腹を減らす方法3選


自腹を減らすための方法は、以下の3つ。
- 保育園で負担してもらえるように相談する
- 少額を自己負担する癖をやめる
- 自腹の当たり前のルールに飲み込まれない
順番に詳しく解説していきます。
方法① 保育園で負担してもらえるように相談する
仕事に必要なものがほしい時は、1度上司に相談してみましょう。自腹に対する認識が、間違った方向にすり替わっていることがあるからです。
自腹で購入している人は「きっと、ダメと言われるだろう」「みんな自分で買っているから、自分で買う決まりなんだろう」と決めつけ、相談すること自体を諦めている人もいるでしょう。しかし相談をすることで、許可がもらえたり、検討してもらえたりしてもらえることは実際よくあります。
相談をする時は、伝え方も大切。ただ「買ってください」と言っても許可が降りにくいので、以下のように、詳しく伝えるようにしましょう。
〇〇の活動で、水色の画用紙を購入したいです。子ども人数分必要なので、10枚購入したいです。100円ショップで5枚入りを前に見かけました。2セット購入したいので、かかる費用はおそらく200円です。
保育園側にとっても経費は大事なお金です。
「購入目的」「購入する数」「予算」などをしっかりと上司に伝えることで、必要性を理解してもらえるようにしましょう。
方法② 少額を自己負担する癖をやめる
材料費は園が負担してくれる場合でも、買いたいものが少額なら「これくらいなら、いっか」と自腹で買ってしまう保育士は多いはず。
例えばふらっとお店に立ち寄った時、ついつい保育に必要なものを買ってしまうことはありませんか?また足りない材料が思い浮かんだ時、100円ショップへ足早に向かった経験はありませんか?
活動で使う材料は100円ショップなどで安く買えるときが多いので、「これくらい大目にみるか」とつい自分のポケットマネーからお金を出してしまう保育士は少なくないと思います。
また「少額のものの購入許可が取りづらい」といった心境から、自腹をきる人もいるでしょう。しかし少額であっても経費は経費です。自分自身が経費として大切に扱わなければ、自腹問題はなかなか解決しません。
方法③ 自腹の当たり前のルールに飲み込まれない
「自腹が当たり前」の保育園は多く存在しますが、そうなってしまう要因として以下2つのことが考えられます。
- 絵本や教材を当たり前のように自腹で購入する保育士がいる
- 「みんな自腹で買ってるよ」と自腹仲間を増やそうとする保育士がいる
あなたはこの「当たり前の連鎖」にのる必要はありません。保育士の給料は低いため、「仕事に関するお金は保育園で負担してほしい」と考えるのは、おかしいことではありません。
自分の意志を大切にして、取るべき行動を選んでいきましょう。



「子どもたちのために、自腹でモノを購入するのが良い保育士だ」と主張する人も中にはいます。考え方を押し付けられないように気をつけてくださいね。
保育士の自腹を減らして、不要な出費を抑えよう!
仕事に必要なものであっても、自腹にするか園の負担にするかは運営者の判断になります。そのあいまいな境界性により、園負担に該当するようなものでも、自腹購入をさせている園は多いはず。
まずは、園の経費のルールを明確にすることから始めることから始めましょう。就業規則を確認してみるでもいいですし、園長に直接聞いてみるでもいいと思います。ルールが分かったら、少額であっても自腹をしないように心がけていきましょう!
もし不必要な出費を減らすことができたら、欲しいものや食べたいものなど自分が喜ぶことにお金をかけてあげてくださいね。
何かのタイミングで転職をする場合は、必要なものが保育園に揃っているかどうかもチェックすると良いでしょう。備品や在庫が充実していれば、自腹の負担を少なくすることができると思います。
また、仕事後にあちこち回って、買い物する機会も減るでしょう。休日の買い出しって残業みたいに仕事に縛られているように感じて、嫌になる方も多いのではないでしょうか。
下の記事は「保育士を辞めたくなる5つの理由と対処法」をまとめたものです。自腹の不満以外にも何か仕事でモヤモヤしていることがあれば、ぜひこちらの記事も参考にしてみてください。